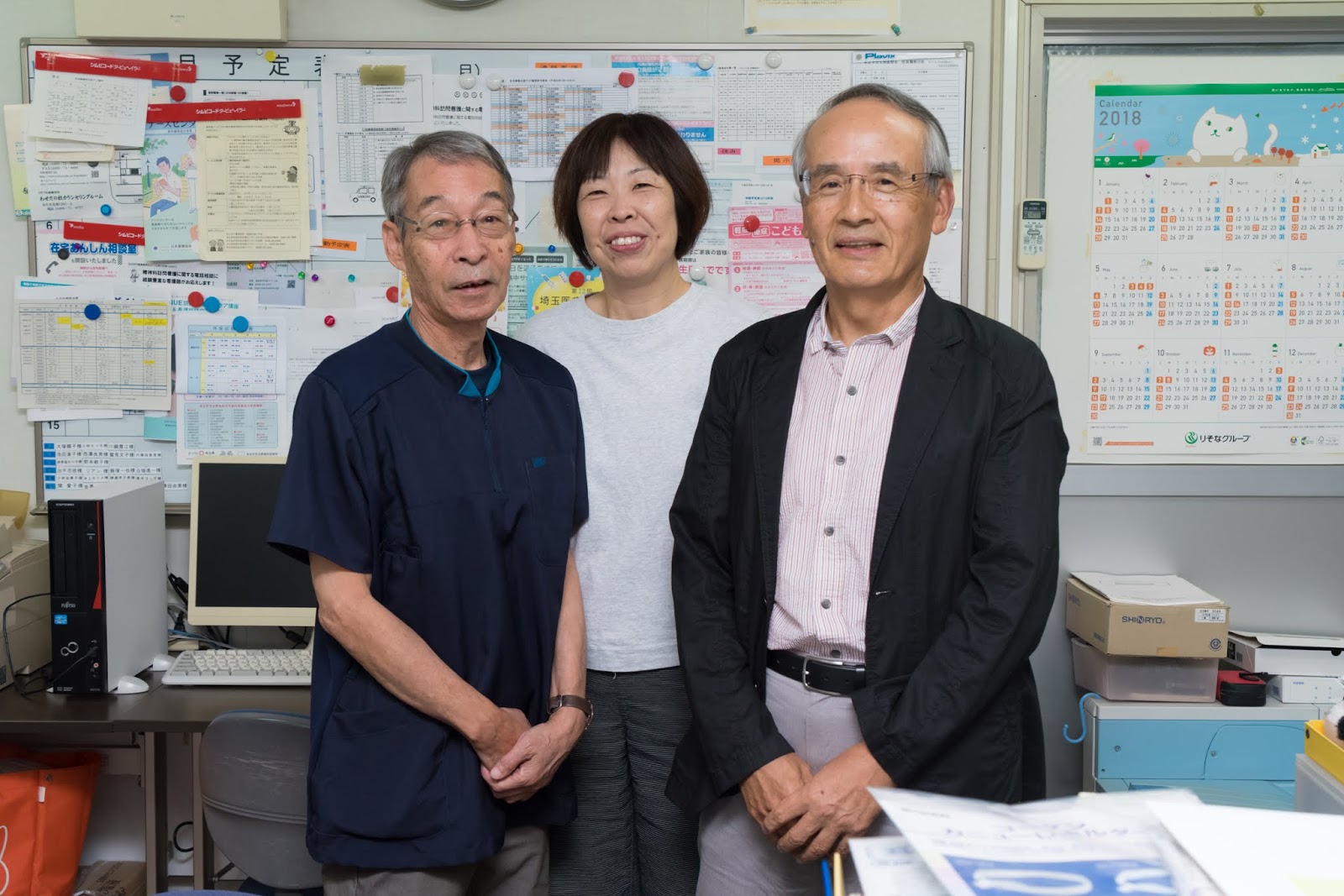
高齢者人口が全国一のペースで増加する埼玉県では、これからの在宅医療を支えるための取り組みとして、県内に33の在宅医療連携拠点を設け、多職種連携によるチーム医療の推進を図っている。2025年を見据えた医療介護問題のソリューションとして、「多職種連携」「主治医・副主治医制」「ICT活用」などが提唱されて久しいが、うまく機能しているケースは全国的にそれほど多くないのが実情だ。そのような中で、県北部の群馬県境に位置する人口約13万人の本庄市児玉郡では、MCS(メディカルケアステーション)の活用による多職種連携が在宅医療において奏功するケースが増えつつあるという。その鍵となったのは、あるひとりの看護師だった。
着実に多職種ネットワークが広がった理由
本庄市児玉郡医師会在宅医療連携拠点の看護師である大沢由美子氏は、「初めてMCSを知ったとき、これを使えば私たちのやりたいことができるんじゃないか、と思ったのです」と振り返る。やりたいこととは、「多職種ネットワーク」と「在宅患者を取り巻くあらゆる医療職・介護職(必要に応じて健康・福祉行政職も含む)のネットワーク」をつくること。彼女は早速動いた。まず着手したのがネットワークの基盤となるMCSでの自由グループづくりだ。最初のうちは情報交換の場の域を出ないかもしれないが、そうしておくことで、実際に運用するときに患者を中心としたチームを組みやすくなる。
大沢氏は、MCSの内容を説明したビラを手作りするなどして、同拠点がカバーする圏域(本庄市、美里町、上里町、神川町)の幅広い職域のスタッフに積極的にアプローチした。自ら端末の操作をレクチャーすることも厭わなかった。その甲斐あって、2018年9月現在、「本庄児玉圏域多職種ネットワーク」の参加者数は252名にのぼる。中でも特筆すべきは、行政の中枢にいる市長や保健所長も参加している点だろう。 「市長に入ってもらって政策でやってもらったらいいんじゃないかと思って、市長室まで乗り込んで登録してもらったんです。今は見ているだけかもしれませんが、一度書き込みもされましたし、会議にも参加されましたよ」※と、大沢氏は事もなげに話すが、これは全国的に見てもレアケースだ。(※編集部注:市長や保健所長は患者情報の閲覧はできません)
こうして築かれた本庄児玉圏域多職種ネットワークが、実際にどのように活用されているのか見ていこう。埼玉県の在宅医療連携拠点制度では、訪問看護や往診を受けている患者が拠点に登録すると支援ベッドを使うことができる仕組みがある。大沢氏はここに目をつけ、拠点に登録している患者を中心にMCSで繋がろうと考えた。まず患者と家族の承諾を得て、看護師が患者情報を登録する。そして患者を取り巻く主治医、副主治医、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどを招待してグループをつくり、家族にも積極的に声をかける。医師も内科、整形外科、精神科医などさまざまな専門医が参加した。 「お互いに面識がないので、まず全員で集まってカンファレンスをやりました。顔合わせですね。ネームプレートをつけて写真を撮り、患者グループのタイムラインに載せました。こうすると、チーム感が出てみんなが書き込みやすくなるんです。何かあったら報告するということではなく、気づいたことを共有しましょうと、MCSの使い方を最初に確認し合いました」
MCSの導入以来、さまざまな連絡時間を大幅に短縮することができた。以前は患者の様子を聞くために15分ぐらい電話で話すことも珍しくなかったが、今は手の空いた時に書き込むだけでよい。いちいちタイムラインを確認するのは負担ではないかとの危惧もあったが、寝る前に一度だけチェックするのを日課にしている医師もおり、日々の習慣にしてしまえば負担ではないようだ。 また、当初はセキュリティの面で不安視する声もなかったわけではないが、富沢峰雄医師(富沢医院)は「紙やファクスでやりとりする方がよほど心配でしょう」と語る。
主治医・副主治医制を超えた「バーチャルホスピタル」の展望
この地域の訪問看護ステーションは小規模で、24時間対応はしていない。在宅医療支援診療所も限られている。しかし、往診できる医師は自分の他にもいるし、もともと医師同士の顔の見える関係性があったと高橋公男医師(高橋外科整形外科)は言う。
「主治医・副主治医制というと、例えば患者が入院していた大学病院の先生が主治医で、退院して地域のかかりつけ医が副主治医になる、というのが一般的な概念でしょう。だけど、この地域では以前からお互いに困ったときに補い合おうという関係性がありました」 こうした協力体制は、MCSの導入によりさらに促進される。基本的には患者の近所の医師が入るが、必ずしも「主」「副」のペアではなく、ケースに応じて診療科を超え何人でも患者グループに参加する。関わっている医療者や介護者が患者の状態をタイムラインで簡単に共有できるため、いろいろな角度からアイデアが出て、結果的に患者の病状回復やQOL向上に結びついた例も少なくない。ここでは主治医・副主治医制はごくあたり前のシステムとして有効に機能しており、そのツールとしてMCSが活用されている。
「24時間対応の訪問看護ステーションが金科玉条とされているけれど、MCSを使った連携の方が内容的には濃いと思いますよ」 と高橋医師。例えば、MCSで共有された情報から推測し、「ハズレ覚悟で薬を持参して」往診したところ、読みが当たってスピーディな対応ができたこともある。こうした準備ができたのもMCSあってのことといえる。 しかし、課題も残る。現場の医師や看護師たちがいま求めているのは、ヘルパーやデイサービスの従事者のMCSへの参加である。最も多く患者と接しているのは彼らだからだ。例えば「顔色が悪い」「いつも食べるものを今日は食べない」といった些細な変化は、わざわざ電話で医師に伝えるのは抵抗がある。しかしタイムラインで共有できれば、より良い対応が可能になる。医師たちにとっても貴重な戦力になるのだ。
注目したいのは、このような医療者同士が互いにカバーし合う仕みが、県境を超えて広がりつつあるという点だ。ある患者をきっかけに、群馬県渋川市の医療機関のスタッフとMCSでつながったケースもあったという。患者の家族もMCSに参加していた。この地域は群馬県境に位置することもあり、治療病院が群馬県内にあるというケースが多いため、藤岡市、伊勢崎市、高崎市など、今後さらに県を越えた連携が広がっていくことが期待される。
医療者・介護者のためだけでなく、家族の安心にもつながる
具体的な取り組み事例を紹介しよう。90代前半、独居の男性のケースだ。主治医を担当したのは富沢氏、副主治医は高橋氏。キーパーソンである患者の長女、長男は遠方に暮らしており、ノート、メール、電話で連絡を取っていたが、大沢氏の声がけにより主治医、副主治医、ケアマネジャーと看護師が参加してMCSを利用した情報共有をスタートさせた。しかし、患者の病状が徐々に悪化してくると、心配した長女から頻繁にメールが届くようになったため、家族にもMCSに参加してもらうことに。大沢氏は当時をこう振り返る。 「とにかく『心配』『心配』という言葉がメールに詰まっていたので、ご家族にも入ってもらいました。すごいなと思ったのは、逐一情報が伝わることで今度は『安心しました』っていう言葉が出てくるようになったんです」
メールで連絡していたときは、何かが起きた時に報告をするという形だったが、MCSはスマホで手軽にアップできるため、大沢氏は日常の細々したことや写真を頻回にアップした。結果、この患者は希望通り自宅で最期を迎え、ご家族からとても感謝されたということだ。患者の家族が安心や感謝の気持ちを伝えてくれることで、ケアするスタッフ全員のモチベーションもアップする。医療介護現場におけるコミュニケーションの大切さが改めて確認できる。
このケースには後日談がある。患者が他界した1週間後にこのグループのやりとりをMCS保管庫に移したところ、長女から「もうタイムラインを見られないのですか」と連絡があったという。MCSで父の様子を見るのが日課になっていた長女にとって、タイムラインが見られなくなるのは寂しかったようだ。 「そこで慌てて保管庫から元に戻し、しばらくは残すことにしました。写真や動画、経過がたくさん掲載されたMCSのタイムラインは、生存中は伝える手段で、他界後は思い出になる。ご家族のグリーフケアにもなると気づいたのです」(大沢氏)
理想の看取りのためには家族との密なコミュニケーションが欠かせない
「今、アドバンス・ケア・プランニングの時代になっているが、患者家族と密にコミュニケーションが取れるようになると、家族の看取りについての温度感がわかってきます」 と話すのは富沢氏。
「最期についての話し合いは必要なのだが、往診で初めて患者や家族に会う際に、いきなり看取りの話などできるものではない。タイミングを見計らって話し合わなければならないという実にデリケートな課題なのだが、MCSの患者グループに家族が参加することで、本人の意思を尊重した看取りへの方向性が見えてくる」という。そのケースを紹介しよう。
患者は胃がんにより胃を全摘出した後、食べられなくなってしまった女性。本人は病院ではなく自宅で自然に最期を迎えたいと希望するのだが、家族としてはそうも言っていられない。当初、同居する長男には自宅で母親を看取る覚悟ができていないように感じられたという。そこで、日頃のケアのためにも長男にMCSに参加してもらった。 例えば患者に傷があったとき、長男が「これでいいですか」と手当てした写真をアップし、それに看護師や医師が「大丈夫ですよ」と返事をする。こうしたやりとりを繰り返すことで家族の不安が解消され、専門職から認められることで介護者としての自信もついてくる。 「つながっている安心感というのは大きいでしょうね。ずっと心配して『先生、来てください』と言っていた息子さんが、やがて『そんなに来なくてもいいですよ』と言うようになったんです」と大沢氏。 「看護師を育てているように」家族も成長するのだそうだ。こうした過程を経たからこそ、家族も納得の上で本人の希望通り最期を自宅で看取れる形に持っていくことができた。
今回取材した本庄児玉郡医師会在宅医療連携拠点には、これからの地域医療に求められる「バーチャルホスピタル」の姿があった。
この記事のポイント!
・埼玉県「本庄児玉圏域多職種ネットワーク」の参加者数は252名まで広がり、行政の中枢にいる市長や保健所長も参加している(2018年9月現在)
・群馬県渋川市の医療機関のスタッフとMCSでつながるなど、医療者同士が互いにカバーし合う仕組みが県境を超えて広がりつつある
・患者の家族が安心や感謝の気持ちを伝えてくれることで、ケアするスタッフ全員のモチベーションが高まる
・患者の写真や動画、経過が掲載されたMCSのタイムラインは、生存中は伝える手段で、他界後は思い出になる。家族のグリーフケアにもなっている
取材・文/金田亜喜子、撮影/池野慎太郎