日本のほぼ真ん中に位置し、自然に囲まれた岐阜県関市。人口88,889人(2019年2月1日現在)のうち、65歳以上が占める割合が29%と高齢化率もやや高め。昔ながらの地域の繋がりがまだ強いこの地域で、医療・介護・福祉のスムーズな連携に貢献しているのが、包括支援センターが開催する毎月の地域ケア会議や、武儀医師会在宅医療介護相談センター(CBICSセンター)の存在だ。平岡医院の平岡哲也医師は、それらの中心人物として地域医療に尽力。多職種の連携を図るコミュニケーションツールとして2015年にメディカルケアステーション(MCS)を導入し、訪問診療以外にもさまざまなケースで積極的に活用している。
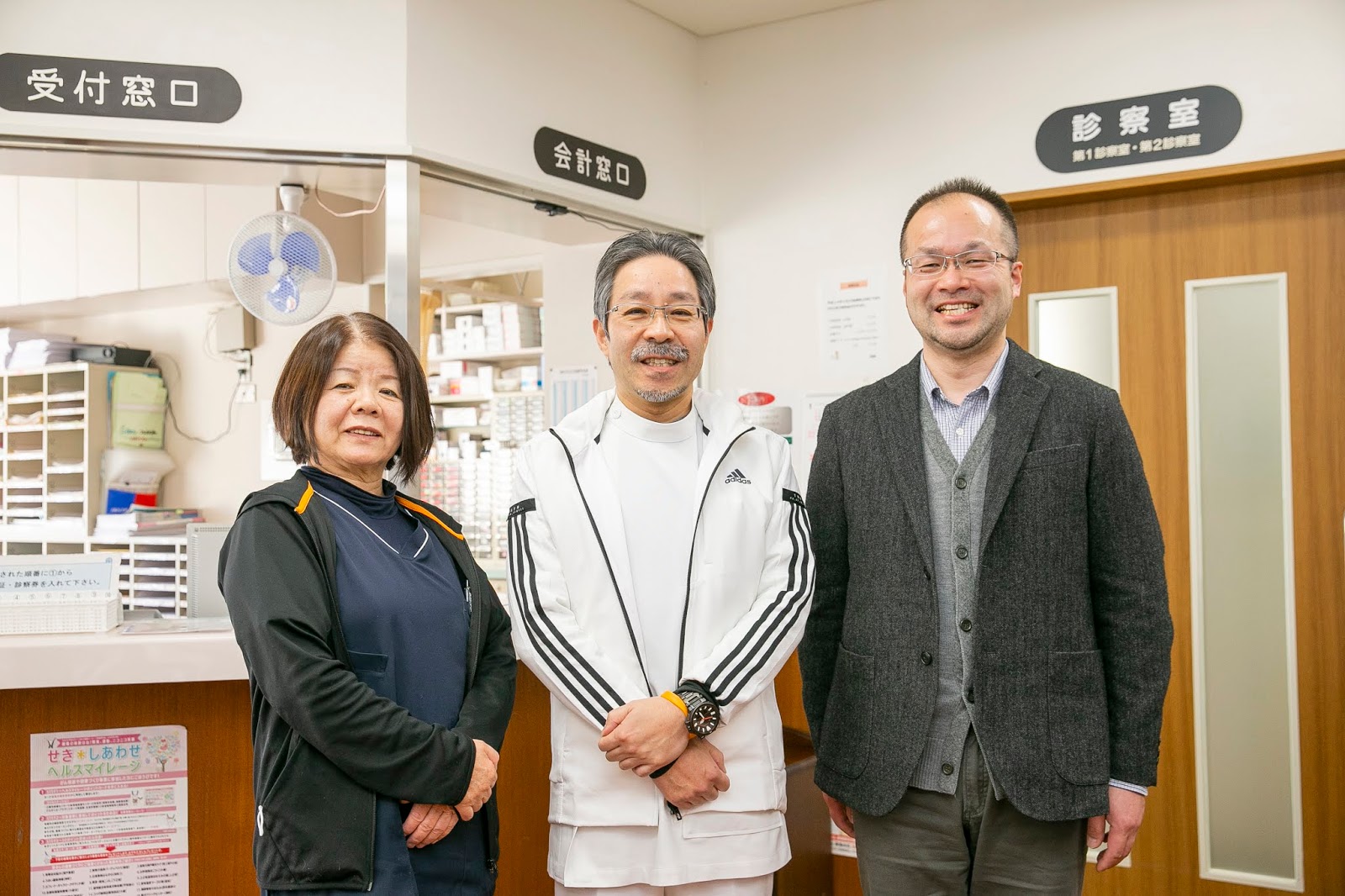
地域のあらゆる福祉をサポートする多職種連携
平岡氏が2006年からメンバーとなっている武芸川町の地域ケア会議は、認知症初期集中支援チーム、包括支援センター、関市職員(住民福祉係・高齢福祉課・保健センター)、社協・生活支援コーディネーター、武芸川駐在所警察官の多職種が連携し、月1回開催されている。「例えば、介護保険が適用できる人は介護保険でカバーできるけれども、その一歩手前の人はどうしたらいいのか、介護する側の家族に精神疾患や知的障害がある場合はどうすればいいのか、といった悩ましいケースがあります。この場合、違う部署の担当者が一つ一つ対応していても、なかなかうまくいきません。縦割りでバラバラに担当するのではなくて、まとめて相談に乗らないといけない。そこを話し合うのがケア会議の役割です。解決が難しい困難事例は複合的な要因が重なっていることが多いので、多方面の関係者が一度に話し合える機会は重要です。武芸川町の場合は、民生委員や警察も入っているので、他地域だと見逃されそうな事例も細かく拾って対応策を立てられます」(平岡氏)
サポートを必要とする人に対して、行政が月1回見にいく程度のサポートではあまり役に立たない。そこで効果的なのは個人のネットワークだ。兄弟関係や親戚、友人や幼馴染み、知り合いなど周囲の人が少しずつ協力して解決にあたらないと、要介護者への細かいサポートは実行できない。「武芸川町では昔ながらの近所付き合いがまだ生きているので、茶飲み友達まで探し当てて、その人に関わってもらうこともあります。この曜日は誰々さんが一緒だから大丈夫とかの詳細レベルまで確認するのです。匿名でケースを取り上げても、こういった周辺情報が得られないので、あまり意味がないのです」。人との繋がりが密なエリアではとくに、”対象がどこの誰なのか”という個人情報が解決に導く重要なポイントなのだ。
認知症初期集中支援チームとMCSで連携
このケア会議ではさまざまなケースが取り上げられ、平岡医院でも関係各所と連携して支援に当たっている。中でも全国的にも問題となっている認知症初期患者への対応は特に注目に値する。関市の場合は、市から委託を受けた社会福祉法人が初期支援の業務を担当しているが、医療ニーズが高いケースが多いため、医療機関との連携は欠かせないという。関市から事業受託している関市認知症初期集中支援チームの社会福祉士・河合誠氏は言う。「最初にチームを立ち上げたとき、医療との連携がうまくできるのだろうかという不安がありました。診療の合間に医師に話を伺うのははばかられることが多いですし。その不安を解消してくれたのが、MCSです。情報の共有ができて、それを支援にすぐ反映できる。我々の支援活動には重要なツールになっています」。
認知症が疑われても、受診を拒否する人は珍しくない。そういう時にスペシャリストとして対応するのが認知症初期集中支援チームだ。平岡医院の患者であった妻が、夫の認知症を疑ったものの、本人が受診を拒否するケースがあった。夫は別の病院に長く通院していたが2カ月ほど通院を拒否していた。妻が病院の主治医に相談したところ、薬は今回だけは出すが次回からは病院では対応が無理なので、よければ近くの平岡医院に紹介状を書くが(どうするか)、と言われる。妻としてはどうしたらいいのかわからない状態。相談を受けた平岡氏は、妻の通院の付き添いという口実で来院してもらい、診察することを提案。しかし、なかなかうまくいかない。そこで、河合氏に相談して連携がスタートする。認知症初期集中支援チームのスタッフが何度も自宅を訪問し、世間話をしながら徐々に患者さんとの距離感を近づけて信頼関係を築き、1年半をかけて最終的に認知症専門医へ受診するまでにこぎづけたのだ。その間、活躍したのがMCSだった。訪問時の状況、職員からの情報、医療情報などを互いにタイムラインにアップし、全体像がリアルタイムで確実に把握できるようになったことで適切な対応を行うことができた。
平岡氏もMCSの利用を始めた当初は、在宅医療以外の患者にMCSを利用するという発想がなかったという。「在宅用という思い込みがあったせいか、そのほかの患者さんで使おうという意識がなかったんですね。このケースで初めて認知症初期集中支援チームとの連携に使ってみたら、これがすごく便利でした。今は誰かと提携したいと思ったら、気軽に自分で患者グループを作っています」(平岡氏)。また、MCSでケアマネジャー(以下ケアマネ)と連携できるメリットもあると言う。「最初は平岡先生とチームだけのグループですが、ケアマネさんと繋がれる状況になったらそこに入ってもらい、その後定着したのをモニタリングし、見届けたところで初期支援チームの業務は終了します。ケアマネさんがMCSに発信してくれる情報のおかげで、現場に出向かなくてもサービスが安定して利用できているかが、すぐに確認できるようになりました」(河合氏)
遠方家族の不安を診立てのアップで解消
平岡医院では患者家族が遠方にいる場合、患者側のタイムラインを活用している。「こういう医療を提供しています、ということを家族に把握してもらうためにMCSに登録してもらっています。提供医療の”見える化”です。遠くの家族には、患者さんがどんな医療を受けているかが、さっぱりわからないんですよね。以前は”なぜ病院に連れても行かずに自宅で死なせた”と言われたこともありました。亡くなったところしか見ていないと、我々が一生懸命やったことを一切知らないままで、それまでの努力も認めてもらえない。そんな状況を避けるための予防線というのではないのですが、これだけやっていますよということをMCSで情報提供することで、わかっていただけるかなと。おかげで、ご自宅で看取りをした患者さんのご家族から”これだけのきめの細かい医療を提供してもらえてありがたかったです”と言っていただけたこともありました。」
とはいえ、医師が医療介護側と患者側の両方のタイムラインに書き込むのは大変なこともあるだろう。「僕は医療側に書き込んだ内容を患者側にコピペするだけなので、ほとんど負担にはなりません。病院で書くカルテをそのままファクスで送るような感じです。末期の患者に対する、本当に専門的な話を医療側だけにアップすることはありますが、それ以外はわざわざ書き直したりせずにコピペしています。家族には了解ボタンを毎回押してもらっているので、見てくれていることはわかります。週に1度くらいは”ありがとうございました、毎回見させていただいています”のようなコメントが入ってきていましたね」。医療介護側、患者側とグループごとにコメントを書き分けるのに比べて、医師の負担は軽く、家族側は正確な情報が得られるので安心できる。とはいえカルテをほぼそのまま患者へ提供し共有しているのは、かなり先進的なことではないだろうか。
こういうケースもあった。一人暮らしに非常に不安を覚えている独居の高齢者が、遠方の家族にも不安を訴えるため、どちらもちょっとしたことがすぐに心配になる。そこでMCSに登録してもらい、平岡氏やふく訪問看護ステーションの看護師・清水環氏が自宅を訪問するたびに、「こういう状況で心配ないですよ」と患者タイムラインに情報をアップするのだ。すると、リアルタイムで状況が把握できるようになり、本人も遠方の家族も安心するようになった。「画像をお送りしたこともありました。例えば、湿疹ができてちょっとかゆいなど軽微な皮膚のトラブルでも、電話だと様子がわかりづらいので、家族も不安になりますよね。でも画像を送って状態を見てもらえば、心配するほどではないことがすぐにわかって安心してもらえます」(清水氏)
反対に、転んだようなので見に行って欲しいという家族からの書き込みがあり、自宅を訪問してみると実は骨折していて、病院に搬送したということもあった。MCSのやり取りだけでなく、気になったことや不安なことがあれば、実際に行って対応してもらえるということが、一層の安心に繋がっている。
誰もが使えることがコミュニケーションツールに必須の要素
武儀医師会が在宅医療介護相談センターを立ち上げた当初、多職種連携のツールとして平岡氏が使用していたのはMCS以外のソフトだった。「在宅用の電子カルテとして機能的に非常に高度なものだったのですが、医師や看護師には使いやすくても多職種のスタッフや患者家族には少しハードルが高かった。医療の専門用語が飛び交っているところへの書き込みを躊躇する気持ちもわかります。一方、コミュニケーションツールに特化したMCSは操作がシンプルなので思ったことを書き込んでもらいやすい。それでMCSに乗り換えました。無料というのもありがたかったですね。今は岐阜県医師会もその有用性に着目しています」。
導入にあたり、武儀医師会から在宅の医療機関と訪問看護ステーションにMCSをインストールしたタブレット50台が無料配布されたが、実際使う側の看護師はどう感じたのだろうか。「最初は抵抗がありました。看護記録もこちらも両方入力しないといけなくなるので。でも実際は、コピペして少し文章を変えるだけなので、慣れれば大丈夫になりました。実際に使ってみると、病院内での医師と看護師のような関係が、平岡医院と訪問看護ステーションで築けることがわかり、とても助かっています。また、患者宅に行かない時でも、ケアマネさんやヘルパーさんからの情報で、状況がすぐわかるのがとてもありがたいです」(清水氏)。結果、医師側のメリットにもつながる好循環が生まれている。「訪問看護師の清水さんが、MCSを介して患者さんとの連携もしっかり取れているので、僕のところに緊急の電話があるのは看取りの時だけになりました」(平岡氏)
毎週開催の認知症カフェも開始
2018年からは隣接のデイサービスで「オレンジカフェ」もスタート。1回100円の参加費で、美味しいコーヒーとお菓子もサービスされる。認知症カフェとは言いながら、近隣の高齢者の方のおしゃべりの場&健康教室的な存在になっているという。地域の喫茶店や小売店が相次いで閉店してしまい、集まって話せるところがなくなってしまったため、カフェがその受け皿となっているのだ。他の認知症カフェは月1回の開催というところが多いが、”毎週やらないと来る人が忘れてしまう”(平岡氏)という。デイサービスのスタッフによる体操やクイズなどのレクリエーションを楽しみにしている人も多い。
「”元気が出ない”と暗い表情で月1回診察にきていた方が、毎週オレンジカフェに来るようになって、目の輝きが変わりました。みんなと一緒にワイワイ話して、大笑いして。ご飯も美味しく食べられるようになったし、夜もぐっすり寝られると言われると、嬉しいですね。認知症なのに介護保険などが使えない人も、カフェで見守り、ケア会議にも報告しています。来てくれている人だけでなく、来なくなった人もちゃんとチェックすることも大切ですね」(平岡氏)
オレンジカフェの参加者にも話を伺ってみた。「おしゃれをして、お化粧をして集まって、みんなで大笑いして楽しめる場です。家にいるとそんなに声をあげて笑うこともないけれど、ここにくると本当に楽しい。認知症の方もいらっしゃいますが、昨日とか明日の話は少し辻褄が合わなくても、カフェに来ているときの会話は楽しんでいますよ。この楽しみはずっと続いてほしいですね」
このように、在宅医療だけでなく、広い意味での地域医療に貢献している平岡氏だが、周りに頼まれてやっているうちに、いつの間にかこうなったと笑う。「初めは在宅も面倒だからやりたくないと思っていたんですね。でも、先輩に言われてこの地域で在宅を始めることになった。デイサービスも周りの要望で作りましたし、医師会の理事になったら、そこでも在宅の担当になってしまった。そうすると、やはり自分が旗を振らないといけなくなる。認知症カフェも最初は断っていたけれど、そこまで言われたら仕方がないと始めたら、おかげさまでこうやって非常にみなさんに喜んでもらえている。周りがやってほしいことをやっていたら、それが結果的に周りの皆さんの喜びに繋がったという30年でしたね」
ケア会議では、地域の困難ケースがよく取り上げられるが、在宅以外のケースでMCSを介して繋がることはまだ少ない。前述したように要介護者の家族に障害があった場合、成年後見人や世話人などにも参加してもらえば、多方面からサポートしやすくなるのでは、とも平岡氏は言う。「あと、小児在宅のケースで、家族の支援に協力できないかという構想もあります。患者のケアは小児の専門医になりますが、家族のサポートなら小児科医以外でもできます。家族は24時間つきっきりで、体調が悪くなってもなかなか病院にもいけない。そんな時、待ち時間なしですぐ医者にかかれるような体制を作るとか」。高齢者の在宅医療支援にとどまらず、あらゆる面で地域を支える存在になりつつある平岡医院の今後に、ますます期待したい。
取材・文/清水真保、撮影/カメイ・ヒロカタ