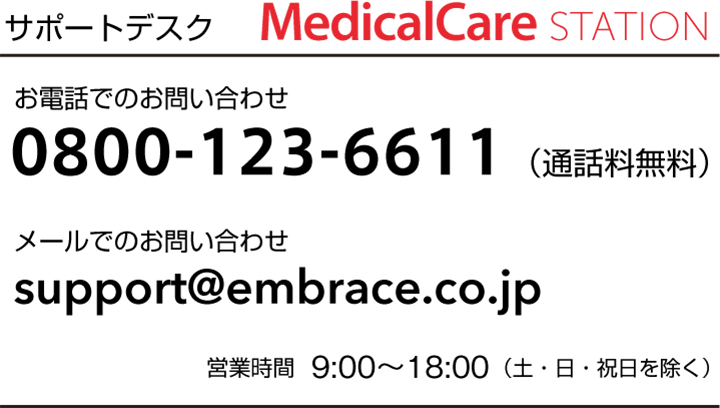現役世代のがん治療における患者と医師のコミュニケーション(東京)前編
日本人の2人に1人がかかると言われるがん。患者は大きな不安に襲われ、藁にもすがる思いで、最新の治療情報を探すものだ。そうした中、ホームドクターとのICTを通じたコミュニケーションによる情報共有で落ち着きを取り戻し、適確な判断ができたと話すのが法政大学教授の長岡健さん。患者と医師との対等なコミュニケーションを通じて、患者はより効率的で納得できる治療を受けることができると語る。2019年からはオンライン診療を開始し、時間の節約にも成功した。2020年2月に治療開始から5年目を迎える長岡さんに、その治療の経緯やICTを通じた医師とのコミュニケーションについて聞いた。

■PROFILE
長岡 健さん(患者)
1964年、東京都生まれ。法政大学経営学部教授。一般企業での勤務を経験した後、海外の大学で博士課程を修了。その後、産能大学教授などを経て2011年より現職。組織社会学/ポストモダン・エスノグラフィーが研究テーマ。2014年秋に、大学の健康診断で食道がんが見つかり、2015年にがん専門病院で化学療法とがん切除手術を受けた。退院後は、東京・自由が丘の山下診療所自由が丘の「よろず医療相談」を受診。2019年3月からオンライン診療を開始した。
がんの発覚からホームドクターと二人三脚で
大学教授の長岡健(たける)さんは、企業における人材育成やコミュケーションなどについて研究する組織社会学の研究者だ。2014年秋に大学の健康診断で食道がんが見つかり、その日のうちに中高の同級生で医師の山下巌氏(山下診療所 自由が丘・大塚 理事長)に連絡を取り、「どこで治療するか」を相談した。「山下先生は、私にとっていわゆるホームドクターという感じで、その4〜5年くらい前から、歯のインプラントや禁煙のことなどで、相談に乗ってもらっていました。山下先生は私のキャラクターもよく知っていたので、『長岡さんは総合病院ではなく、がん専門病院のほうがいいだろう』とアドバイスされました。退院後の生活や後遺症についても山下先生がチームを組んでフォローするから心配しないでということで、東京都内のがん専門病院に紹介状を書いてもらい、受診しました」。
がん専門病院での最初の診察のあと、長岡さんはセカンドオピニオンを取ることも検討したが、早く治療を受けることが優先と考え、その病院で治療を受けることを決断する。食道がんが発覚してから約1カ月後の2014年11月から同病院へ入院し、化学療法をスタートし、翌年2月には外科手術を行った。
この間、様々な不安を抱えた長岡さんが山下氏に相談する際に使用したのがFacebookのメッセンジャー機能だ。がん専門病院の検査結果や医師に言われたこと、自分が感じた疑問などを山下氏にメッセンジャーで送り、返事をもらっていたという。「申し訳ないなとは思ったのですが、こちらも命がけで背に腹は代えられないので、疑問に思ったことはすべて山下先生に聞いていました。山下先生も診察中は返事ができないので、診察が終わった夜に返事をくれました。結果的にはこうして相談したことが成功だったと思います。不安なことや分からないことはすべて山下先生に相談して、その情報を元に最後はすべて自分で決めました」。
長岡さんは、ホームドクターの存在の重要性と、疑問に思った時にその都度問い合わせができ、互いに負担の少ないメッセンジャーという「非同期のコミュニケーション」が功を奏したと語る。
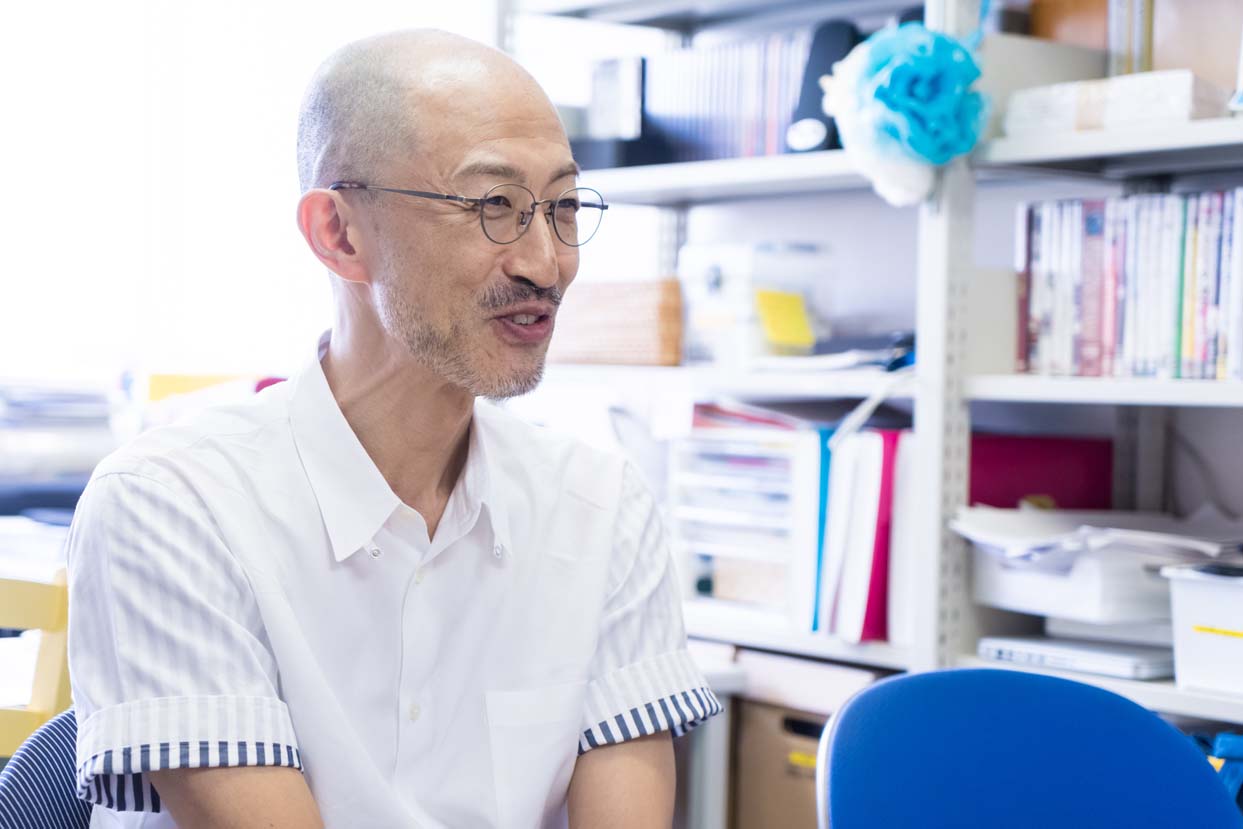
医師との対等なコミュニケーションのための付箋メモ
がん専門病院で治療を開始した長岡さんは、山下氏の言う「がん専門病院のほうがいい」という意味をすぐに実感することになる。「がん専門病院の医師は非常に歯切れがいいんです。『5年生存率はどのくらいですか』と聞くと『55%くらい』、『再発後の1年生存率は』と聞くと『18%くらい』とはっきりと言ってくれますからね。この先生は信頼できると思いました。そういう信頼できる先生と、さらに山下先生ともSNSで繋がっているという、非常にいい環境でした」。実は、長岡さんの父親にもがんの闘病経験があり、その当時は本人に告知もせず、治療方針についても患者には決定権がないという時代だった。「40年ほど前のことですが、そういう経験があったので、自分はきちんと医師とコミュニーションを取って、納得して治療を受けたいという思いがありました」。
2014年11月には同病院に入院し、化学療法を開始、2015年2月には手術を受けることになっていたが、入院中のエピソードがユニークだ。同病院では、毎日朝食後に主治医の回診がある。長岡さんは日々、疑問に思ったことをその都度付箋に書き込んで、ベッドに設置されているテーブルに貼っておき、朝の回診の際にその疑問を主治医にぶつけたのだ。たとえば、「自分の手術の縫合には、ステープラーを使用するのか、それとも手縫いなのか」「高濃度ビタミンCが効くというのは本当か」という質問など、とにかくすべての疑問を書き溜めていた。「朝の回診は、手術や急患があると、日によって時間が前後します。ちゃんと準備しておかないと、疑問点を忘れてしまったりするんです。医師ときちんとコミュニケーションするにはこちらも準備が必要で、ぼーっとしているときに『何かありますか』と言われても『何もありません』と答えるしかなくなるので、それを避けるために付箋は有効でした。日々の体調のことはもちろんですが、がんの標準治療の本を読んで気になったこと、ネット検索で医学論文などを読んで疑問に思ったことなどを全部付箋に書き、主治医に質問しました」。
長岡さんは、「医師との対等なコミュニケーション」を強調する。特にバリバリ働いているビジネスパーソンのような現役世代は、情報検索にも慣れており、自分で調べ、医師と話して納得しなければ治療を受けようとはしないはずという考えだ。幸いなことに、主治医は怒ったり、嫌がったりすることなくすべての質問に答えてくれ、退院が近づくにつれ、「他には質問はありませんか」と聞いてくれるまでになった。こうした質問の形は、長岡さんがメッセンジャーで山下氏に送っていた質問のアナログ版だ。病院ではそれしか選択肢はなかったと長岡さんは語る。「唯一、不便だったのはネットのURLを手書きでは書き切れなかったこと。デジタルなら、すぐに見てもらえますが、手書きだとなかなか難しいし、スマホの画面を医師に見せて説明しようとしても小さくてよく見えなくて、それがストレスでしたね」。
さらに、長岡さんは、この付箋のメモをスマホで写真に撮り、主治医の回答とともにメッセンジャーで山下氏に送り、情報を共有した。「主治医の意見を聞いて、そのあと山下先生の意見を聞くということをくり返していくとやっぱり落ち着きますよね」。医師とのコミュニケーションを通じて、患者の中には安心が醸成されていくのだ。
なかでも、この情報共有がもっとも役立ったのが、手術をするかしないかの判断だった。「私は抗がん剤の効きがいいタイプで、抗がん剤の治療によって目視上はがんが消えるまでになりました。こんなに抗がん剤が効くなら、手術しないで、抗がん剤治療だけでもよいのではないかとも考え、最後まで悩みました」。
結局、長岡さんは手術することを選択するのだが、その際に決め手となったのが、手術前面談時の主治医の言葉だったという。「主治医は、『抗がん剤が効いて、予想通りの効果が出ているときは標準治療で行くべきだという信念が自分にはある。標準治療を支持するエビデンスが出ているときに、それを覆すような方法を取るのは科学的な考え方ではない』と言ったんです。この人は腹をくくっているなと感心しました」。だが、長岡さんはその場では結論を出せず、そのあと、山下氏にメッセンジャーで相談した。「山下先生は常にニュートラルで、様々なアドバイスをしながら、私の悩みにずっと付き合ってくれました。最後に私が『このまま標準治療の手術を受けてみようと思う』と言ったら、『それでいいと思う』と山下先生が言ってくれて、それで手術を受けることを決めました」。
主治医をどんなに信頼していても、できれば手術を避けたいと思うのは患者に共通の思いだ。その不安を取り除く方法として、長岡さんの迷いに最後まで寄り添ってくれたホームドクターの存在は重要だった。たとえ、それがメッセンジャーという非同期のコミュニケーションであっても、大病院に一人で入院する長岡さんには強い味方だった。
取材・文/豊岡昭彦、撮影/池野慎太郎
※今回の取材に際し、長岡氏は治療を受けたがん専門病院の名前の公表を希望されていましたが(他メディアや研究会では具体的病院名を公表されています)、病院側の掲載許可が得られなかったため、発行側の判断により病院名を伏せさせていただきました。