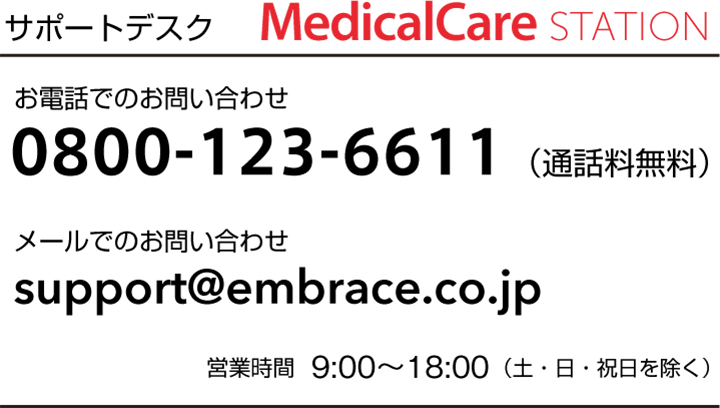小児在宅を支える、病院・学校も含めた多職種連携(東京)後編
【前編はこちら】
小児在宅を支える、病院・学校も含めた多職種連携(東京)前編

病院や学校ともMCSで連携し、修学旅行への参加も実現
成人の在宅医療ではケアマネからの紹介が多いが、小児の場合はほとんどが病院からの紹介だ。染色体異常などの先天性の病気をもつ子供が多く、NICUから直接退院することもあれば、いったん小児科病棟への入院を経て退院することもある。退院前カンファレンスは何度も繰り返し行われ、最初のカンファレンスは退院の3カ月前ぐらい。「何カ月ぐらいの月齢で退院させたいという目標があるので、そこに向けて準備を進めるためにカンファレンスを重ねます。赤ちゃんはその間にも成長するため、退院時に必要な医療機器が最初の頃とは変わっているということもありますから」(小畑氏)。
小児在宅を始める前からMCSを導入していた同クリニックでは、関わる全ての小児患者についてMCSの患者グループを作成し、多職種との情報共有を欠かさない。小児在宅の場合は定期的に通院することが多いため、可能な限り病院の主治医にもMCSに参加してもらう。そうすることで在宅での情報を主治医が常に把握することができ、また通院時の情報は関わる多職種にタイムリーに共有される。通常、病院の医師は外部と情報のやりとりをする習慣がないのだが、小児科には担当する子供を常に気にかけている医師が多く、小畑氏がMCSについて説明して依頼すると、多くは快く参加してくれるそうだ。現在も、東京都内と埼玉県内の病院の多数の医師と繋がっている。
中には病院側の事情によってアカウントを取得できない主治医もいるため、その場合の連絡手段は電話やファクスになる。「でも、それでは何かが起きた時にしか連絡できません。MCSなら『今日何を食べました』『元気にしています』などトラブルのない普段の様子も伝えることができて、ニコニコ笑っている写真も送ることができます。訪問看護師さんたちは私たちよりもっと患者さんと接しているので、より多くの情報を伝えてくれます。なにより、会ったことのない多職種のメンバーであっても顔の見える連携を図れるところがいい」と話す小畑氏は、MCSのメリットは時間的な効率化よりも、圧倒的な情報量の多さにあると考えている。患者家族が訪問看護師に何気なく話した言葉まで伝わると、医師はそれに合わせたアプローチができるため、間違いなく医療の質自体が上がるというのだ。


小児在宅医療に関わる多職種は訪問看護師、薬剤師、歯科医、管理栄養士、リハビリ職など一般的な在宅医療と変わらないが、細かなケアが必要なため訪問頻度が多く、1人の患者に複数の訪問看護ステーションが入ることもある。そのほか、小児の特徴として学校との連携も挙げられるが、学校のなかにはルールが厳しく子供のケアへの協力的が難しい場合もある。学校としては極力リスクを回避したいために、通学させてくれない、行事に参加させてくれない、ということが起きてしまうのだ。「できない原因の多くは学校の先生たちの不安から来るので、私たちがサポートすることで安心感を与え、対応してもらえるようになることもあります。常に私たち医療者が見守っていることを知って安心してもらう意味でも、学校の先生をMCSにお誘いすることがあります」(小畑氏)。学校の教員は医師と同じく電話連絡が難しいためMCSの有用性は高く、積極的なところでは学校での子供の体調などを報告してくれることもあるという。
小畑氏らが学校側を説得して、修学旅行への参加が可能になった例もある。患者は特別支援学校に通うAさん、中学生、重症てんかん、慢性呼吸不全。MCSには在宅チームのほか担任の教員と、その上長にあたる教員が参加していた。首都圏のテーマパークへの日帰り修学旅行が予定されており、Aさんは参加を希望したが、通学実績が少ないことなどを理由に学校から参加を断られてしまった。そこで在宅チームはなんとか参加できるよう、ビデオ会議システムを利用して授業を受けさせたり、MCSを使って丁寧に学校側とコミュニケーションを重ねたり、さまざまなサポートを行なった。その結果Aさんは、クリニックの医師が1人同行するという条件で修学旅行に参加できたという。「もしMCSがなかったら、あれほど細かいコミュニケーションは取れないので断られていたでしょう」と小畑氏は振り返る。
高齢者のケース同様、小児在宅であっても緩和ケアや看取りは無縁ではない。染色体異常の場合は1歳になる前に亡くなることが珍しくなく、乳児のうちにがんにかかってしまう子供もいるからだ。しかも小児の場合、保護者に対するメンタルケアも重要で、関わる多職種の密な連携が必要になる。同クリニックでは、様々な面で敏感になっている家族が多く、家族に対しては大切なことは会って直接説明するため、家族のMCS参加は想定していない。むしろ、家族にどう伝えるかということを事前に多職種で共有するのがMCSの役割で、特に看取りが近くなると家族への対応は非常に慎重になる。たとえば看取りを覚悟した家族が「心停止しても救急搬送はしない」と一度は心を決めても、いざとなるとやはり「見捨てられない」と救急搬送を希望するケースは珍しくない。その後、何度も同じことを繰り返す場合もある。小畑氏はじめクリニックのスタッフは、どんなに家族の気持ちが変化しても、最後までしっかり寄り添ってケアを継続するという姿勢で患者・家族と向き合っている。
MCSはそのプロセスにおいて不可欠なツールであり、成人のケース以上に密に細かくやりとりを重ねる。さらにMCSの書き込みに疑問があれば電話も併用し、コミュニケーションの質を上げていく。こうした手厚いサポートのベースにあるのは医療介護者の患者を思う気持ちだ。その気持ちは家族にもしっかり伝わるようで、看取りのあと担当医に感謝のメッセージとともにアルバムやビデオレターが送られてくることもあるという。

家族やペットと過ごせる自宅こそ本来の居場所
これまで小児の経験がなかった多職種メンバーも、MCSで情報共有するうちに小児に関する知識が増えて急速に成長するという。そもそも小児在宅を経験したことのある事業所は少ないので、同クリニックが依頼して、一般の在宅医療に携わる事業所に関わってもらうことが多い。そのような経緯で連携した事業所のスタッフが、MCSを使って一度小児在宅を経験すると、急速に小児に対応できるようになり、次に繋がるのだという。自分の担当していない患者のタイムラインを見ることで、医師をはじめあらゆるスタッフの経験値が上がるため、これもMCSのメリットのひとつといえる。小児在宅の受け皿がまだまだ不足している中、このように少しずつでも受け入れ体制が整っていくことが重要だ。
今後、さらに小児在宅医療の受け入れが拡大していくために何が必要か小畑氏に聞いてみたところ、「病院の医師にもっと在宅医療でできることを知ってほしい」との答えが返ってきた。「小児に限らないかもしれませんが、在宅で治療なんてできないと思っている病院の先生はまだまだたくさんいます。だから退院が選択肢に入らないし、病院の先生が言えば家族だって退院できないと思い込んでしまいますが、ほとんどの場合、在宅で診られるんです。緩和ケアは病院よりも私たちのほうが得意なくらいで、それは自宅の方が患者さんが安心できるからということもあります。病院の先生にとっては病院が普通の場所になってしまっていますが、患者さんの本来の居場所は両親、兄弟姉妹やペットと一緒に過ごせる自宅なのです」。小畑氏の小児在宅への取り組みが、より多くの小児科医の間で周知されることが望まれる。
取材・文/金田亜喜子、撮影/杉本晴
【前編はこちら】
小児在宅を支える、病院・学校も含めた多職種連携(東京)前編